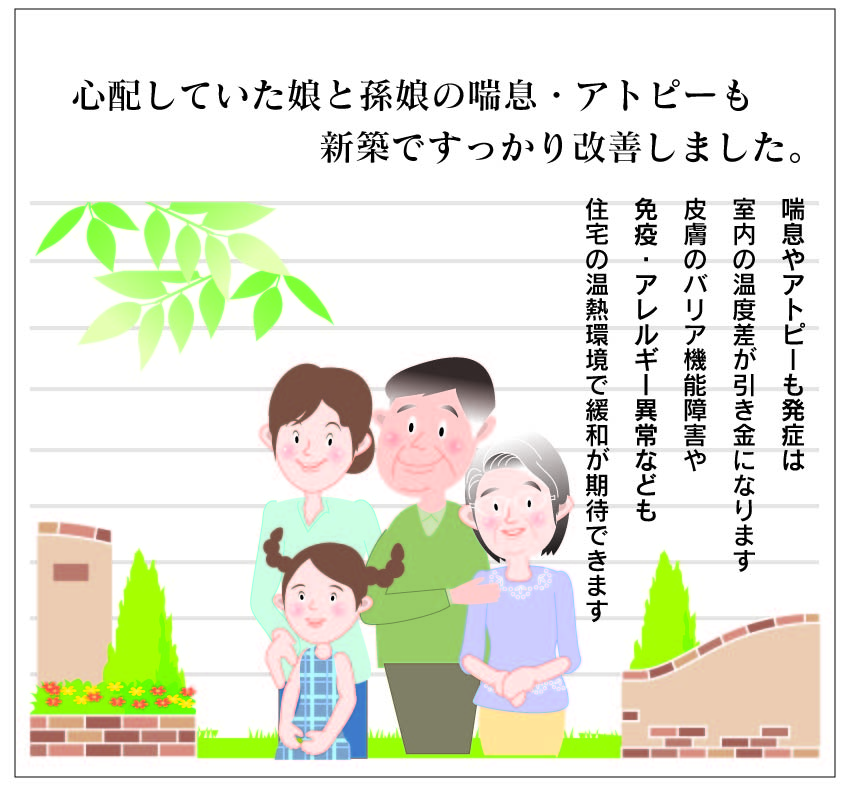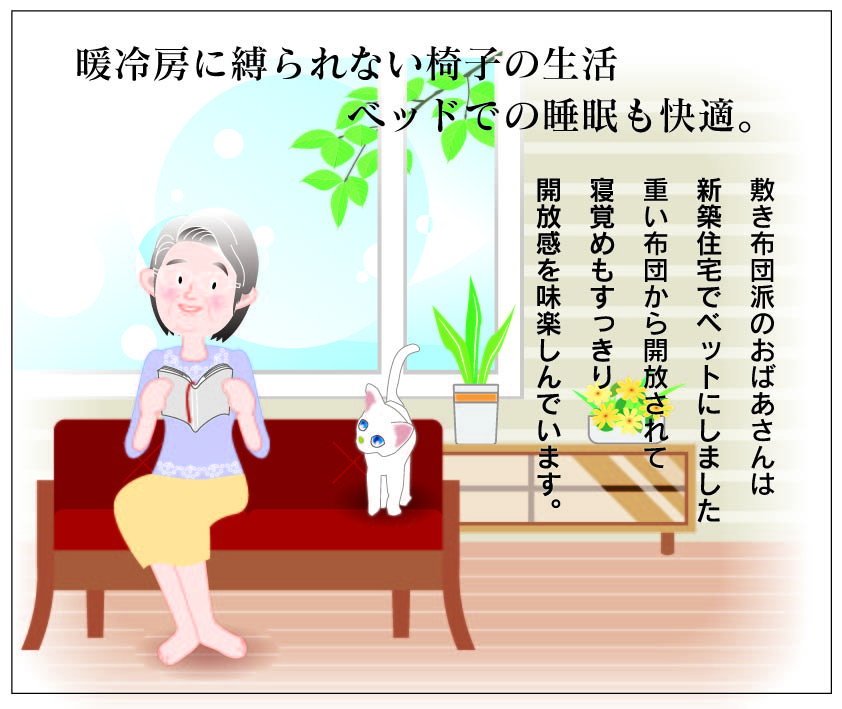なぜ草原住宅は“平屋スタイル”にこだわるのか?
フランク・ロイド・ライトは世界的な建築家で、日本でも旧帝国ホテルなど歴史的な建物を建てたことで知られています。しかし日本人がロイドの建物を愛したのは学校や一般の家屋に、日本人の感性を刺激する自然との調和を第一に考えた建物を建てたからです。ロイドには日本人の弟子も多くプレーリーハウスなど、ロイドの思想を体現した建築家、田上義也などもいます。このプレーリーハウスをリスペクトして「草原住宅」は誕生しました。自然との調和を目指した低高層の建物は必ずしも平屋ではありませんが、ロイドが日本家屋の繊細さに触発させられて設計したもので、老後の動きもしっかりと考えられた、加齢に伴う変化と環境が調和できる建物でした。各階への移動は最低限の階段で移動でき、まるで平屋にある凹凸を認識させる程度の負荷しか掛からず、幼児も年寄りも無理なく移動が可能なように考えられています。勿論、二階建てもお建てしますが「草原住宅」が平屋スタイルにこだわりがあるのは、究極のバリアフリーだからです。ロイドは、住宅のアップダウンを最低限にしたプレーリーハウスで老若男女のバリアフリーを実現しています。
自然とつながる、ひらかれた暮らし
私たちが大切にしているのは、「家族の健康」と「自然との調和」、健康と経済性を両立した住まいです。
草原住宅の家族の健康に寄り添う住まいの考え方をもっともよくかたちにできるのが、水平に広がる開放的な空間を併せ持つ“平屋スタイル”という健康と省エネ性を両立した住まい。
なぜ平屋住まいなのか? それには理由があります。
それは、ただの流行や見た目の好みではなく、暮らしの安心や快適さ、そして人生の変化にも寄り添うための、シンプルですが長く愛されるこれからの住まいの本質と言いますか深い意味があるのです。
この考え方の原点には、ある一人の建築家の存在があります。
世界的にも有名な建築家、フランク・ロイド・ライトです。
フランク・ロイド・ライトが教えてくれたこと
フランク・ロイド・ライトは、アメリカを代表する建築家。
日本でも、旧帝国ホテルを設計したことで知られています。
しかし、ライトが本当にすごいのは、建物と自然との“つながり”をとても大切にしたことです。
「建物は自然の中に溶け込むようにあるべきだ」という考え方は、まさに私たち草原住宅がめざす住まいのあり方と通じています。
なかでも彼が手がけた「プレーリーハウス(草原の家)」という住宅スタイルは、まさにその象徴。
ゆるやかに横に広がる低層の家は、周囲の景色と調和し、住む人の心と身体をやさしく包み込むように設計されています。
このプレーリーハウスの考え方に触れたとき、わたしたちは確信しました。
――これこそが、これからの日本の家族に必要な住まいのかたちだ、と。
平屋住まいだからこそ叶えられる、暮らしの安心
草原住宅が“平屋”にこだわるのは、デザインや見た目のためだけではありません。
平屋は、家族みんなが「今もこれからも」安心して暮らせる住まいだと考えているからです。
たとえば、こんなシンプルなメリットがあります:
-
階段がない、または最小限なので移動がラク
→ 足腰が弱くなってきたご家族や、小さなお子さまにもやさしい動線設計になります。
-
家族の気配を感じやすい
→ フロアが分かれていないぶん、生活の中で自然とコミュニケーションが生まれます。
-
将来的なそれぞれのリフォームにも柔軟に対応できる
→ 住まい方の変化にも順応しやすく、「建てたら終わり」ではない家づくりができます。
草原住宅では、家事動線や将来を見すえた“ライフステージ設計”を意識しています。お子さまが小さなうちは家族が一緒に過ごす空間を中心に、成長に合わせて個のスペースを確保したり、シニア世代になっても身体に負担のない動線で生活できるように――。
そのすべてが、平屋という住まいのかたちに込められているのです。
さらに草原住宅では、共働き世帯の家事ストレスを軽減する工夫も大切にしています。
たとえば、キッチン・洗濯・収納・玄関まわりをぐるりと回れる「回遊型の家事動線」は、移動のムダを省いて毎日の家事効率をぐっと高めてくれます。
料理しながら洗濯や子どもの支度を見守れる動線は、時間に追われがちな平日の朝にも、ゆとりと安心を生み出してくれるのです。
こうした“暮らしやすさの仕組み”も、バリアフリー性と並んで、草原住宅の平屋に込めた大切な価値のひとつです。
平屋住まいは「究極のバリアフリー」
フランク・ロイド・ライトの住宅では、階段があってもほんのわずか。
段差は最小限で、まるでなだらかな土地を歩くように自然に移動できます。
わたしたちも、この考え方を大切にしています。
草原住宅の家は、段差を感じさせない動線設計でつくられています。
1〜2段のステップで空間に変化をつけつつも、身体に無理のない設計。
平屋であっても、視線の抜けや光の広がりをつくることで、狭さを感じさせない工夫をしています。
こうしたつくりは、加齢による身体の変化や、妊娠・子育て期など、
さまざまなライフステージにおいて「心地よさ」と「安全」を両立してくれます。
だから私たちは、平屋を「究極のバリアフリー住宅」と呼んでいます。
二階建ても、草原住宅らしい“やさしさ”を
もちろん、土地の条件やご希望によっては、二階建てをご提案することもあります。
その場合でも、草原住宅が大切にしている「自然との調和」「家族の健康」「暮らしやすい動線設計」の考え方は変わりません。
たとえば、階段の勾配をゆるやかにしたり、1階だけで暮らしが完結できる間取りにしたり。
年を重ねても安心できる工夫をしっかりと取り入れています。
これからも、“自然と人にやさしい住まい”を
私たちの草原住宅の「草原」という名前には、これからの住まいのあり方
大地とともに、澄んだ空気や爽やかな風とともに、すこやかに生きていく暮らしへの願い、穏やかな暮らしへのが想いが込められています。
自然と調和しながら、家族の健康と未来にやさしく寄り添える住まい。
それが、私たちが平屋スタイルにこだわる理由です。
これからも私たちは、フランク・ロイド・ライトの思想に学びながら、
熊本・合志の「健康住宅」草原住宅の平屋住まいプロジェクトをご提案してまいります。